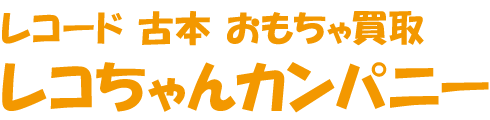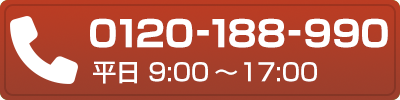レコード買取のレコちゃんカンパニーが教えるレコード豆知識
こんにちは。株式会社レコちゃんカンパニー代表の塚本です。
レコード査定歴がやっと20年になりました。
そんな私のちょっとした知識と、専門書やネットで調べた情報などをわかりやすくお伝えしたいと思います。
最近レコードに興味を持った方、レコードが好きな方の一助になれば幸いです。
レコード会社とレーベルの違いについて
今回は、よく聞くけどちょっとわかりにくい「レコード会社」と「レコードレーベル」の違いについて。
この二つの名称、混同されることが多いのですが全く別の意味です。
「レコード会社」はまさしくレコードを制作する会社のこと。
「レコードレーベル」はブランド名であり、場合によってはレコード会社間で譲渡されることもあります。
次の章でもう少し詳しく解説しましょう。
レコード会社はレコードを企画、制作する会社のこと
レコードを売り出すには、まず「企画」→「音源を制作」→「レコードを製造」→「告知宣伝」→「レコード店に卸す」→「皆さんの手元に販売」という流れがあります。
その中で「企画・制作・宣伝・卸売り」するのがレコード会社の主な仕事です。
レコードの製造、生産はまた別の「レコード製造会社」「プレスメーカー」が行います。
日本のレコード会社としては、「日本コロムビア株式会社」「キングレコード株式会社」「株式会社ソニーミュージックレーベルズ」などなど、一般社団法人日本レコード協会に加盟している会員がおもな「レコード会社」となります。
同協会のホームページを見ると、正会員が18社、準会員が22社となっており、このへんが「日本のメジャーなレコード会社」といっても良いでしょう。
無論、協会に加盟していないレコード会社もあります。いわゆるインディーズ系、独立系などと呼ばれたりします。
レコードレーベルとは「ブランド名」のこと
例えば先に挙げたソニーミュージックレーベルズという会社の事業内容にはこう記されています。
音楽・映像ソフトの企画、制作、宣伝を行なうレコード会社。
株式会社ソニーミュージックレーベルズの事業内容より
アーティストの発掘・育成からマネジメント、音源制作、マーケティング、メディアプロモーションまで一貫した戦略によってアーティストの音楽活動全般をプロデュースし、国内外に向けて幅広く発信するレーベルビジネスを展開。多様な個性を持った複数の音楽レーベルによって構成されています。
つまり、レコード会社の中の「ブランド」として、各種のレーベルが存在するわけです。
例えばソニー系でいえば、現在は「ソニーレコード」「ジーアールエイトレコード」「SMR」などのレーベルがあります。
過去には(私はこちらの方が馴染みがありますが)「エピック」「フィッツビート」「オデッセイ」「ソニークラシカル」などのレーベルがありました。
レーベルはレコード会社が変わることもある
時代の変遷で、あるいはその他の事情で会社は事業の選択と集中という経営判断を行います。
そのなかに「ブランド」としてのレーベルが、レコード会社(に限りませんが)間で譲渡されることもあります。
例えば大瀧詠一さんの個人的なレーベルだった「ナイアガラレコード」は、当初ソニーミュージックで扱っていましたが、大瀧さん亡き後、レーベルの所有は親族に移りました。
また、ジャズの名門レーベルブルーノートは1967年に日本で最初に東芝音楽工業から国内盤の製造、販売が開始されましたが、70年代後半にキングレコードに移り、80年代にはまた東芝EMIに戻り、現在はユニバーサルミュージックが販売するというふうに変遷しています。
レコードのレーベルとレコード会社の違いについてのまとめ
いままで簡単に見てきたように、レコードの「レーベル」と「レコード会社」は全く違うものである。
ということがお判りいただけたかと思います。
もっと深く、専門的かつ趣味的に掘り下げていくと、レコード会社の変遷、レーベルの変遷というのは映画や小説のような面白さがあります。アーティストと経営者の協調と対立。こういった視点で音楽業界を見ると、とても情熱的で、お金だけではない人間臭さが垣間見えますよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。